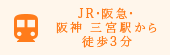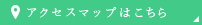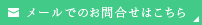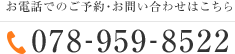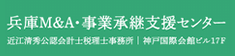<事例>
Aさんは配偶者Bと長男C,長女Dが推定相続人でした。
長女Dの結婚後、Dの夫であるEとAは養子縁組をしました。
Aは、相続税対策として自らの財産を減らすため
相続時精算課税を利用してC,D,Eに均等に金融財産の贈与を
行いました(金額は2500万円以上)。
しかし、BはAの財産がCDEの3名に均等に贈与されると
長男CがAから贈与される財産よりも、DE夫婦がAから贈与される
財産の方が多くなることが納得できませんでした。
そもそもBは、DEの結婚も反対していました。
最近では、BはAE間の養子縁組を離縁するか、あるいは
Aの相続発生時にはEは相続放棄をするか、どちらかを
Eに要求するまでになりました。
さて、Bの要求に基づいて離縁するか相続放棄をする場合に
Eの課税関係はどうなるでしょうか。
<解説>
今回の事例は、相続税精算課税の適用時には推定相続人であった者が
実際の相続開始時には、相続人ではなくなった場合に相続税精算課税の適用が
どのような扱になるのか、という論点です
結論から申し上げますと、EはAさんと養子縁組を協議離縁しても
EがAさんの相続開始時に相続放棄しても、相続税精算課税を選択して
Aから贈与された金融財産(2500万円以上)については、Aの相続税計算時に
相続税の課税対象となります。
相続税精算課税制度を選択する場合、「相続時精算課税選択届出書」を
税務署に提出します。(相続税法21条の9第2項)
相続時精算課税を選択した者は、上記選択届出書を提出後に推定相続人
ではなくたったとしても、相続時精算課税制度が適用されて税額の計算を
行うことになります(相続税法21条の9第5項)
さらに相続時精算課税選択届出書は、一度提出するいかなる場合でも
撤回はできません(相続税法21条の9第6項)
このように一度選択すると後戻りできないのが、相続時精算課税制度です
一般的には、時価変動の影響を受けにくい預貯金の贈与に相続時精算課税制度を
利用する場合が多いようです。
短期的な贈与税の節税という視点だけで判断するのではなく、
財産の構成・相続税の節税対策・さらには2次相続の対策まで検討してから
相続時精算課税の選択を慎重に検討する必要があります。
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/